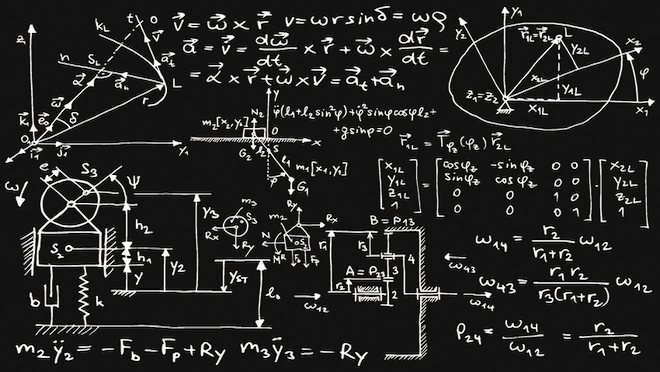vagrant userがdockerに入門するためのチートシート
vagrantを知っていてこれからdockerに入門する方向のチートシートを書く。 dockerコンテナの方が小さいので基本的に粒度が合わないが、 対称性を重視して似た機能を並べてみた。 コマンド一覧(vagrant list-commands)からメジャーなのをピックアップした。 Dockerコンテナのネットワーク設定等、概念違いで比較しづらいものは除いた。 また、各コマンドにはパラメタが必要だが煩雑になるため省略した。 vagrant box / docker image操作 vagrant docker boxの一覧vagrant up imageの一覧docker images boxの追加vagrant box add */*imageの追加docker pull imageの詳細docker inspect * boxの削除vagrant box remove *imageの削除docker rmi * boxの更新vagrant box update */*imageの更新docker pull * 全boxの更新vagrant box update imageからbox初期化vagrant init * imageのタグ設定docker tag * vagrant 仮想マシン操作/コンテナ生成/起動/停止 vagrant docker 仮想マシン起動vagrant upコンテナ生成/起動docker run コンテナバックグラウンド実行docker run -d コンテナ起動docker start 仮想マシン終了vagrant haltコンテナ停止docker stop 仮想マシン再起動vagrant reloadコンテナ再起動docker restart 仮想マシン一時停止vagrant pauseコンテナ中断docker pause 仮想マシン再開vagrant resumeコンテナ再開docker unpause 仮想マシン削除vagrant destroyコンテナ削除docker rm 仮想マシンステータス表示vagrant status 全マシン一覧vagrant global-status稼働コンテナ一覧docker ps -a 仮想マシンログインvagrant ssh スナップショット(vagrantのみ) vagrant スナップショット作成vagrant snapshot save * スナップショット復元vagrant snapshot restore * スナップショット削除vagrant snapshot delete * スナップショット一覧vagrant snapshot list dockerコンテナはホストと共有する範囲が大きく、全環境で完全に同じように動かすことは 難しいかもしれない。 vagrantとdockerは排他的な存在ではなく、vagrant上にdockerコンテナっていう構成もありえる。 Vagrantfile, Dockerfile関連は次回...
tmux – ssh接続先をtmuxのペインに表示する
昔使っていた.tmux.confが失われてしまったため、新しいものを作っていく。 不要な機能が満載になっていたので、これを機に必要なものだけ設定する。 複数の鯖にsshで繋ぐと、ssh接続のペインだらけになり、間違えて操作してしまうことが多い。 その対策として、ssh接続ごとにペインの背景の色を変えていた。 結局、間違えるときは色を変えたところで間違えるため、デザインがケバくなるだけで無意味。 ペインに接続先ホスト名を表示するぐらいがちょうど良い感じだと思う。 こちらの完成度が超絶高いので使うことにしてみた。 ホスト名が強調されたりするともっと良いのだけれども。 SSH接続先のホスト名をtmuxのペインに表示する(大事件) #!/bin/zsh #/usr/local/bin/tmux-pane-border if [[ $1 = \"ssh\" ]]; then pane_pid=$2 info=$({ pgrep -flaP $pane_pid ; ps -o command -p $pane_pid; } | xargs -I{} echo {} | awk \'/ssh/\' | sed -E \'s/^[0-9]*[[:blank:]]*ssh //\') port=$(echo $info | grep -Eo \'-p ([0-9]+)\'|sed \'s/-p //\') if [ -z $port ]; then local port=22 fi info=$(echo $info | sed \'s/-p \'\"$port\"\'//g\') user=$(echo $info | awk \'{print $NF}\' | cut -f1 -d@) host=$(echo $info | awk \'{print $NF}\' | cut -f2 -d@) if [ $user = $host ]; then user=$(whoami) list=$(awk \' $1 == \"Host\" { gsub(\"\\\\.\", \"\\\\.\", $2); gsub(\"\\\\*\", \".*\", $2); host = $2; next; } $1 == \"User\" { $1 = \"\"; sub( /^[[:space:]]*/, \"\" ); printf \"%s|%sn\", host, $0; }\' ~/.ssh/config ) echo $list | while read line; do host_user=${line#*|} if [[ \"$host\" =~ $line ]]; then user=$host_user break fi done fi ssh_hostname=\" ssh:$user@$host \" fi echo $ssh_hostname # .tmux.conf set-option -g pane-border-status bottom set-option -g pane-border-format \"#P #(tmux-pane-border #{pane_current_command} #{pane_pid})\" 上記のサイトの通り、各ペインのセッションがsshであればペインのボトムにhostnameを表示している。 sshコマンド自体に手を入れたくないので、process listをポーリングするやり方に賛同します。 次回はシステムのクリップボードコピー。
n次元超球体の体積
[mathjax] 球面集中現象理解のための数学シリーズ第2弾。 前の記事でデカルト座標->極座標の変換から体積要素の積分により3次元球体の体積を導出してみました。 極座標の3変数(r,phi_1,phi_2)について定積分を計算していくと(frac{4pi r^3}{3})が出てきます! [clink url=\"https://ikuty.com/2019/08/02/concentration_on_the_sphere_1/\"] より高次元の超球体の体積がわかると、超高次元のときに体積が超球体の表面に集中する様が 論理の飛躍なく理解できるらしいので、今回は高次元の超球体の体積を導出するやつを流してみます。 (n)次元空間において以下を満たす点の集合が半径(r)の(n)次元球体です。 (x,y,z...)とやっていくとアルファベットが尽きるので(x_1,x_2,cdots,x_n)とします。 (3次元だとすると、半径が(sqrt{x_1^2+x_2^2+x_3^2}le r)の全ての点。) begin{eqnarray} x_1^2+x_2^2+cdots+x_n^2 le r^2 end{eqnarray} この集合を全部足したものが体積になります。 例えば3次元のとき、前回の記事の通り以下のようになります。ここではデカルト座標(x,y,z)。 極座標変換することで計算ができます。 begin{eqnarray} int_{x^2+y^2+z^2 lt r^2} U(x,y,z) dV &=& int_{0}^{2pi} Biggl( int_{0}^{pi} Bigl( int_{0}^{r} U(r,phi_1,phi_2)r^2 sin(phi_1) dr Bigr) d phi_1 Biggr) dphi_2 \\ &=& frac{4}{3} pi r^3 end{eqnarray} ちなみに2次元球体の体積(つまり円の面積)は当たり前ですが(pi r^2)です。 1次元球体の体積(つまり直線の長さ)は(r)です。 なんとなく(n)次元だと(r)の次数が(n)になりそうですが、 実際そうで(時間がないので公式として使ってしまいます)、 (n)次元の超球体の体積は(r^n)に比例します。 (Vr^n)のようにしておきます。 (n)次元の超球体を輪切りにすることを考えます。 球をどうやって輪切りにしても断面図は真円ですので...。 3次元の球体を輪切りにすると2次元の平面が現れる、というイメージです。 (n)次元の超球面を輪切りにし(n-1)次元の平面を作成し、 (n-1)次の平面と微小距離(Delta r)をかけて(n)次元の直方体を作ります。 微小距離(Delta r)を限りなくゼロに近づけることで体積要素とします。 体積要素は詰まるところ輪切りですが、輪切りなのに(n)次元なのです。 体積要素を全範囲で積分することで体積を求めます。 さて、(x_1^2 + x_2^2 + cdots + x_n^2 = 1)が半径1の単位球です。 これを輪切りにします。(n)次の変数を定数にします。(x_n=t)。 つまり、輪切りは(x_1^2 + x_2^2 + cdot + x_{n-1}^2 = 1-t)。 輪切りの半径は(sqrt{1-t})。(t=0)であれば丁度球体を真っ二つにする感じです。 (t=1)であれば球体のキワの限界で面積がゼロ。 (t)で輪切りにしたあと、(t)を微小距離(t+Delta t)だけ増やします。 その体積は(V_{n-1}(sqrt{(1-t)^{n-1}}) Delta t)。 (Delta t)を限りなくゼロに近づけると真の輪切りに近づき、 それを(r)の全範囲で定積分します。 begin{eqnarray} V_n=int_{-1}^{1} V_{n-1}sqrt{(1-t)^{n-1}} dt end{eqnarray} 球体は真ん中で対照なので、 begin{eqnarray} V_n =2 int_{0}^{1} V_{n-1}sqrt{(1-t)^{n-1}} dt end{eqnarray} 計算してから積分するのと、積分してから計算するのが同じなので、 begin{eqnarray} V_n=2 V_{n-1} int_{0}^{1} sqrt{(1-t)^{n-1}} dt end{eqnarray} 超絶懐かしい置換積分を使うと(int f(x) dx = int f(g(t)) frac{dx}{dt} dt)が出来る。 (t=sintheta)とすると、 begin{eqnarray} V_n= 2 V_{n-1}(int_{0}^{frac{pi}{2}} cos^{n-1}theta cos theta d theta ) end{eqnarray} これどうやって積分するんだよ...、と呆然としてしまうけれども、 公式があるようです。時間がないので公式を使います! 階乗が2つ並んでいるのは1つ飛ばしで階乗をする2重階乗というらしい。 begin{eqnarray} int_{0}^{frac{pi}{2}} sin^n x dx &=& int_{0}^{frac{pi}{2}} sin^{n-1}x sin x dx \\ &=& frac{pi}{2} frac{(n-1)!!}{n!!} end{eqnarray} ちなみに(cos^n x)の積分は(sin^n x)の積分から導かれて以下のようになる。 begin{eqnarray} int_{0}^{frac{pi}{2}} sin^n x dx = int_{0}^{frac{pi}{2}} cos^n x dx = begin{cases} frac{(n-1)!!}{n!!} & nが奇数 \\ frac{pi}{2} frac{(n-1)!!}{n!!} & nが偶数 end{cases} end{eqnarray} 体積の話に戻ると、 begin{eqnarray} V_n = begin{cases} 2V_{n-1}frac{(n-1) (n-3) (n-5) cdots 2}{n (n-2) cdots 3} & nが奇数 \\ pi V_{n-1} frac{(n-1)(n-3)(n-5)cdots 3}{n (n-2) (n-4) cdots 2} & nが偶数 end{cases} end{eqnarray} 偶数のときと奇数のときで別になってしまっているのを1つにしたい。 偶数のとき(n=2k)、奇数のとき(n=2k-1)とおいて、それが等しいとする。 begin{eqnarray} V_{2k-1} &=& 2V_{2k-2} frac{(2k-2)(2k-4)(2k-6)cdots 2}{(2k-1) (2k-3) cdots 3 } \\ V_{2k} &=& pi V_{2k-1} frac{(2k-1)(2k-3)(2k-5)cdots 2}{2k (2k-2)(2k-4) cdots 2} end{eqnarray} 2つの式で(V_{2k-1})が現れるので、それで等式を立てる。 begin{eqnarray} 2V_{2k-2} frac{(2k-2)(2k-4)(2k-6)cdots 2}{(2k-1) (2k-3) cdots 3 } = frac{V_{2k}}{pi} frac{2k (2k-2)(2k-4) cdots 2}{(2k-1)(2k-3)(2k-5)cdots 2} end{eqnarray} ガンガン約分する。 begin{eqnarray} V_{2k} = 2pi V_{2k-2} frac{1}{2k} = frac{pi V_{2k-2}}{k} end{eqnarray} (V_{2k})と(V_{2k-2})の漸化式になっていて、(V_{2k-2})が(V_2)になるまで再帰的に計算する。 begin{eqnarray} V_{2k} = frac{pi^{k-1}}{k!} V_2 = frac{pi^k }{k!} end{eqnarray} 階乗の一般化(ガンマ関数,(n! = Gamma{(n+1)}))を使って書くと、 begin{eqnarray} V_n = frac{pi^{frac{n}{2}}}{Gamma{(frac{pi}{2}+1)}} end{eqnarray} (n)次の超球面の体積が出ました...。 次回、これを使って超高次元でメロンパンの皮が厚いのを示します..。
PHPで統計アプリを作れるか否か
LaravelをAPIサーバにして同期的にsklearnのPCAを実行するアプリを作ってみました。 jQyery/bootstrap/chart.jsがフロント、APIサーバはLaravel+MySQL。 Laravel製APIがGET/POSTに対してPythonコードを実行します(Shellで...)。 exec()でPythonを起動するため無茶苦茶重いし、 ろくにエラーハンドリングできません。 結論から書けば同期的なアプリをこの構造で作るのは無理があります。 バックエンドが無茶苦茶重くてどうせバッチ実行になるのであれば、 上記の問題は結構問題なくなって、これでも良いかなと思い始めます。 MS系のInteroperabilityで、多言語が動的に結合するやつがありますが、 あんな感じでLL言語をglueできれば楽なのになと思います。 PSRの多言語拡張みたいなやつで、PHPからPythonのクラスを使うとか...
球面集中現象を理解するために必要そうなことの理解 – 極座標・直行座標変換,
[mathjax] 球面集中現象を理解するために記憶にないことが多すぎるので 理解に必要そうなことを少しずつ復習していきます。 まず極座標の直行座標変換。極座標を使って球の体積を求めてみます。 次の記事で球の体積を求める時に使う微小体積がヤコビアンになることを確認します。 極座標の直行座標変換 2次元のとき、極座標((r),(phi)) を直行座標で表すと、 begin{eqnarray} x &=& r cos(phi) \\ y &=& r sin(phi) end{eqnarray} 3次元のとき、極座標((r),(phi_1),(phi_2))を直行座標で表すと、 begin{eqnarray} x &=& r cos(phi_1) \\ y &=& r sin(phi_1) cos(phi_2) \\ z &=& r sin(phi_1) sin(phi_2) end{eqnarray} ここまではイメージできるのだけれども、(N)に飛ばしたときにどうなるのか。 N次元のとき、極座標((r),(phi_1),(phi_2),(cdots),(phi_{N-1}))を直行座標で表すと 以下のようになるらしい。 begin{eqnarray} x_1 &=& r cos(phi_1) \\ x_2 &=& r sin(phi_1) cos(phi_2) \\ x_3 &=& r sin(phi_1) sin(phi_2) cos(phi_3) \\ vdots \\ x_{N-1} &=& r sin (phi_1) cdots sin(phi_{N-2}) cos(phi_{N-1}) \\ x_{N} &=& r sin (phi_1) cdots sin(phi_{N-2}) sin(phi_{N-1}) end{eqnarray} この後使わないけれど、逆変換は以下の通りになるらしい。 begin{eqnarray} r &=& sqrt{x_1^2 + cdots + x_{N-1}^2 + x_N^2} \\ phi_1 &=& arccosfrac{x_1}{sqrt{x_1^2 + cdots + x_{N-1}^2 + x_N^2}} \\ phi_2 &=& arccosfrac{x_2}{sqrt{x_2^2 + cdots + x_{N-1}^2 + x_N^2}} \\ vdots \\ phi_{N-2} &=& arccos frac{x_{N-2}}{sqrt{x_{N-2}^2 + x_{N-1}^2 + x_N^2}} \\ phi_{N-1} &=& begin{cases} arccos frac{x_{N-1}}{sqrt{x_{N-1}^2+X_N^2}} & X_N ge 0 \\ -arccos frac{x_{N-1}}{sqrt{x_{N-1}^2+X_N^2}} & X_N lt 0 end{cases} end{eqnarray} 3次元極座標系における体積計算の例 極座標((r),(phi_1),(phi_2))において(r)を微小量(Delta r)だけ増やす。 (2pi r)は半径を(r)とする円の直径だということを考慮すると、 (phi_1)から微小角(Delta phi_1)増やしたときの(r Delta phi_1)は円弧の一部。 (Delta phi_1)を限りなく小さくすると(r Delta phi_1)は直線と考えられる。 (2pi rsin(phi_1) )が半径を(rsin(phi_1))とする円の直径と考えると、 (phi_2)から微小角(Delta phi_2)増やしたときの(r sin(phi_1) Delta phi_2)は円弧の一部。 (Delta phi_2)を限りなく小さくすると(r sin(phi_1) Delta phi_2)は直線と考えられる。 (Delta r, Delta phi_1, Delta phi_2)が限りなくゼロに近くときに 上記のそれぞれの直線を辺とする直方体ができる。その体積を(dV)とすると、 begin{eqnarray} dV &=& Delta r cdot r Delta phi_1 cdot r sin(phi_1) Delta phi_2 \\ &=& r^2 sin(phi_1) Delta r Delta phi_1 Delta phi_2 end{eqnarray} 直交座標(x,y,z)の位置を(U(x,y,z))とする。 直交座標系における球の体積はざっくり以下で表せる。 begin{eqnarray} int U(x,y,z) dV end{eqnarray} 直行座標の極座標変換は前述の通り以下。この座標を(U(r,phi_1,phi_2))とする。 begin{eqnarray} x &=& r cos(phi_1) \\ y &=& r sin(phi_1) cos(phi_2) \\ z &=& r sin(phi_1) sin(phi_2) end{eqnarray} 極座標系において以下だから、 begin{eqnarray} 0 le r le 1 \\ 0 le phi_1 le pi\\ 0 le phi_2 2pi end{eqnarray} それぞれについて積分すると体積になる。 begin{eqnarray} int_{0}^{2pi} Biggl( int_{0}^{pi} Bigl( int_{0}^{1} U(r,phi_1,phi_2)r^2 sin(phi_1) dr Bigr) d phi_1 Biggr) dphi_2 end{eqnarray} つまり以下。 begin{eqnarray} int U(x,y,z) dV = int_{0}^{2pi} Biggl( int_{0}^{pi} Bigl( int_{0}^{1} U(r,phi_1,phi_2)r^2 sin(phi_1) dr Bigr) d phi_1 Biggr) dphi_2 end{eqnarray} ここで( U(r,phi_1,phi_2) =1 )として積分範囲を(r)とすると球の体積の公式になる。 begin{eqnarray} int U(x,y,z) dV &=& int_{0}^{2pi} Biggl( int_{0}^{pi} Bigl( int_{0}^{r} r^2 sin(phi_1) dr Bigr) d phi_1 Biggr) dphi_2 \\ &=& int_{0}^{2pi} int_{0}^{pi} Bigl( int_{0}^{r} frac{sin(phi_1)}{3} bigl[ r^3 bigr]_{0}^{r} Bigr) dphi_1 dphi_2 \\ &=& int_{0}^{2pi} int_{0}^{pi} frac{r^3 sin(phi_1)}{3} dphi_1 dphi_2 \\ &=& int_{0}^{2pi} -frac{r^3}{3} bigl[ cos(phi_1) bigr]_{0}^{pi} dphi_2 \\ &=& int_{0}^{2pi} frac{2r^3}{3} dphi_2 \\ &=& frac{2r^3}{3} bigl[ phi_2bigr]_{0}^{2pi} \\ &=& frac{4pi r^3}{3} end{eqnarray} 次回、微小体積とヤコビアンが等しい理由を書いてみます。
sklearnとmatplotlibでsihoutte係数を見てみようとして失敗した話とyellowbrick
[mathjax] sihoutteって何て読むのか...と思うけども\"シルエット\"だそう。フランス語源。 ポートレート写真を背景白、顔を黒に減色した例の\"シルエット\"。\"輪郭\"みたいな。 データ達を複数のクラスタに分割したとして、各々のデータがそのクラスタに存在することの 収まりの良さを表すことができる。 本来(相対的に)他のクラスタに属しているべきデータ達の割合が分かったり、 クラスタ境界で(相対的に)どちらのクラスタに属しても良さそうなデータ達の割合が分かったりする。 sklearnは教師なしクラスタリングまでで、それをグラフ化しないといけないのだけど、 matplotlibに対応するのがなく、\"線を書く\"みたいなコマンドを並べて作っていかないといけない様子。 yellowbrickというパッケージを使うとそれもやってくれる。 Yellowbrick is a suite of visual diagnostic tools called “Visualizers” that extend the Scikit-Learn API to allow human steering of the model selection process. In a nutshell, Yellowbrick combines scikit-learn with matplotlib in the best tradition of the scikit-learn documentation, but to produce visualizations for your models! sklearnとmatplotloibだけで出力するバージョンと、yellowbrickで出力するバージョンの 両方を試してみた(前者はクラスタのラベルを出力できずsihoutteグラフとの対応関係が理解できずに 中途半端で終了)。 sihoutte係数 全データ達は(x_i)。データ(x_i)がクラスタ(A)に属し、最近傍にクラスタ(B)があるという状況。 (A)のクラスタ中心は(x_A)、(B)のクラスタ中心は(x_B)。 \"最近傍のクラスタ中心との距離の平均\"から\"自分のクラスタ中心との距離の平均\"を引いた値。 わざわざ1行に全ての変数が出てくるように書いてみる。 begin{eqnarray} s_i = frac{sum_{i=1}^{n}|x_i-x_B|/n - sum_{i=1}^{n}|x_i-x_A|/n }{max bigl{sum_{i=1}^{n}|x_i-x_A|/n,sum_{i=1}^{n}|x_i-x_B|/n bigr}} end{eqnarray} データが(n)個あるので、sihoutte係数も(n)個できる。 自分が属しているクラスタ(A)よりも、隣のクラスタ(B)の方が居心地が良いと 分子はマイナスになる。 今属しているクラスタでも隣のクラスタでも、どちらもさほど居心地が変わらないとゼロ近辺になる。 大きければ迷いなく今のクラスタで良いことを表せる。 sklearnとmatplotlibだけでsihoutte係数 乱数で作った偽データに6-meansをかけた図。 どうやってもクラスタ中心のラベルが取り出せない!!..(スルー..) import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt import seaborn as sns mu = [[0,0], [20,20], [50,50], [40,30], [40,10], [20,40]] sigma = [ [[30,20],[20,50]], [[20,30],[10,20]], [[60,40],[20,20]], [[60,20],[20,60]] ,[[30,10],[10,30]],[[50,20],[20,50]] ] points = 100 clusters = [] for index in range(len(mu)): cluster = np.random.multivariate_normal(mu[index], sigma[index], points) dig = np.full((points,1),index+1, dtype=int) cluster = np.hstack((cluster,dig)) clusters = np.r_[clusters,cluster] if len(clusters) > 0 else cluster plt.scatter(x=clusters[:,0], y=clusters[:,1],c=clusters[:,2]) from sklearn.cluster import KMeans model = KMeans(n_clusters=6, init=\'random\',max_iter=10) y_km = model.fit_predict(clusters[:,:2]) labels = model.labels_ centers = model.cluster_centers_ centers fig = plt.figure() ax1 = fig.add_subplot(1,1,1) ax1.scatter(x=clusters[:,0], y=clusters[:,1],c=labels) ax2 = fig.add_subplot(1,1,1) ax2.scatter(x=centers[:,0], y=centers[:,1], alpha=0.5,s=600,c=\"pink\",linewidth=2,edgecolors=\"red\") sklearnとmatplotlibだけでsihoutte係数のグラフを出してみる。 \"線を書く\"みたいなコマンドを並べて規格通りの図を作るのか...。 from sklearn.metrics import silhouette_samples # cluster数 num_clusters=6 #全データのsilhouette係数を取得 silhouette_vals = silhouette_samples(clusters[:,:2],y_km,metric=\'euclidean\') cluster_labels = np.unique(y_km) min,max = 0,0 yticks = [] for i,c in enumerate(cluster_labels): c_silhouette_vals = silhouette_vals[y_km == c] c_silhouette_vals.sort() max += len(c_silhouette_vals) plt.barh( range(min,max), c_silhouette_vals, height=1.0, edgecolor=\'none\' ) yticks.append((min+max)/2.) min += len(c_silhouette_vals) avg = np.mean(silhouette_vals) plt.axvline(avg, color=\'red\', linestyle=\"--\") plt.yticks(yticks, cluster_labels + 1) plt.ylabel(\'Cluster\') plt.xlabel(\'Silhouette coefficient\') plt.show() 全体的に茶色のクラスタのsilhouette係数が低め。 残念ながら、どのクラスタと対応するのか出力できず何の考察も出来ず...。 yellowbrickでsilhouette係数を出力 無茶苦茶簡単に出せる。 from yellowbrick.cluster import SilhouetteVisualizer sv = SilhouetteVisualizer(model) sv.fit(clusters[:,:2]) sv.poof() 出てきた図。自作したものと全然合っていないように見える.. 自作したものとラベルが合っていないだけだと信じたい。 似た形の塊があるので.. 以上、完全な失敗だけれども一旦終了...
エルボー法とは , サンプルデータへの適用例
k-means法を実行する際に妥当なkを決めたいという欲求があります。 クラスタ集合の凝集度を定量化することでkと凝集度の関係を得られます。 複数のkについてkと凝集度の関係を取得し、 そこから妥当なkを発見する方法がエルボー法です。 この記事においては以下を書いてみます。 クラスタ集合の凝集度を定量化する方法 kと凝集度の関係を表すグラフの書き方 クラスタ集合の凝集度を定量化する方法 これ以上無いくらいシンプルなやり方です。 データポイントとcentroidの距離の2乗和(SSE)を凝集度として使います。 それを全クラスタに関して計算し足し合わせます。 足し合わせた値を歪み(distortion)と言っているところが多いです。 クラスタ数kが増えるにつれてこの値は小さくなるだろうと予測できます。 横軸にk、縦軸にSSEの和をとるグラフを書いてみると、 kの増加に伴ってSSEの和が小さくなること、減少幅は次第に小さくなりそうです。 (すべてのケースでそうなるのかは不明) 減少幅が緩やかになる地点のkが費用対効果が高いkですし、 ほぼ減少が止まる(サチる)地点のkを採用することは、 それ以上kを増加させても意味がないという事実を根拠として使えそうです。 擬似データへの適用 前回から使っている多次元正規分布に従う擬似クラスタデータに対してk-meansを適用します。 k=1から9まで適用し、k-distortionグラフを書いてみます。(だいぶPythonに慣れてきた..。) import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt import seaborn as sns mu = [[0,0], [20,20], [50,50], [40,30], [40,10], [20,40]] sigma = [ [[30,20],[20,50]], [[20,30],[10,20]], [[60,40],[20,20]], [[60,20],[20,60]] ,[[30,10],[10,30]],[[50,20],[20,50]] ] points = 100 clusters = [] for index in range(len(mu)): cluster = np.random.multivariate_normal(mu[index], sigma[index], points) dig = np.full((points,1),index+1, dtype=int) cluster = np.hstack((cluster,dig)) clusters = np.r_[clusters,cluster] if len(clusters) > 0 else cluster plt.scatter(x=clusters[:,0], y=clusters[:,1],c=clusters[:,2]) from sklearn.cluster import KMeans kmeans_model = KMeans(n_clusters=6, init=\'random\',max_iter=10).fit(clusters[:,:2]) labels = kmeans_model.labels_ distortions = [] numClusters = 10 for i in range(1,numClusters): kmeans_model = KMeans(n_clusters=i, init=\'random\',max_iter=10) kmeans_model.fit(clusters[:,:2]) distortions.append(kmeans_model.inertia_) plt.plot(range(1,numClusters),distortions,marker=\'o\') plt.xlabel(\'Number of clusters\') plt.ylabel(\'Distortion\') plt.show() 複数の擬似点を中心に2次元正規分布に従う散らばりをもったデータ達です。 k-distortionグラフです。もの凄い期待通りなグラフができました。 k=5か6あたりでdistortionがサチっています。 6-meansを適用し、centroidを重ねてみました。 散布図を見ての想像になりますが、 確かに4-meansと5-meansでは、5-meansの方が凝集していそうです。 5-meansと6-meansだと、4と5程凝集度合いに変化がなさそうです。
階層型クラスタリングとdendrogram / 空間拡散性、単調性の確認
前回適当に作ったデータを使って階層型クラスタリングを試してみる。 階層型クラスタリングの様子をdendrogramというツールを使って可視化できるのと、 クラスタ間距離の違いによってクラスタの作られ方が大きく変化することを dendrogramの違いを見ながら確認してみる。 テストデータを作る データは前回と同様に以下のように作る。 import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt import seaborn as sns mu = [[0,0], [20,20], [50,50], [40,30], [40,10], [20,40]] sigma = [ [[30,20],[20,50]], [[20,30],[10,20]], [[60,40],[20,20]], [[60,20],[20,60]] ,[[30,10],[10,30]],[[50,20],[20,50]] ] points = 100 clusteres = [] for index in range(len(mu)): cluster = np.random.multivariate_normal(mu[index], sigma[index], points) dig = np.full((points,1),index+1, dtype=int) cluster = np.hstack((cluster,dig)) clusteres = np.r_[clusteres,cluster] if len(clusteres) > 0 else cluster plt.scatter(x=clusteres[:,0], y=clusteres[:,1],c=clusteres[:,2]) dendrogram 階層型クラスタリングの可視化を行う方法の1つとしてdendrogramがある。 葉(=各データポイント)から始まり、クラスタがまとまっていく様を木構造で表した図。 根は全てのデータポイントを1つのクラスタで表した状態。 左部分木と右部分木に1度別れるところが2つのクラスタに別れた状態。 グラフの縦軸はクラスタ間距離を表していて、dendrogramによって各クラスタの離れ度合いがわかる。 from sklearn.preprocessing import StandardScaler from scipy.cluster.hierarchy import linkage, dendrogram, fcluster SS = StandardScaler() scaled_clusters = SS.fit_transform(clusteres) result = linkage(scaled_clusters, method = \"ward\") dendrogram(result) plt.show() クラスタを作っていく際にどうクラスタ間距離を設定するかで木の構造がだいぶ変わってくる。 空間拡散性 以下はクラスタ間距離として最短距離法を使った場合。 (クラスタ間距離としてそれぞれに含まれるデータポイント間の距離の最小値) 1度併合してクラスタが大きくなると、次に、そのクラスタと隣のクラスタがくっつきやすい。 (データ数が多すぎてよくわからないけれど)下のdendrogramは 右、その1つ左、その1つ左...というように、右から順番に併合する傾向が強いのがわかる。 つまり1度クラスタが作られると、そのクラスタは次のクラスタになりやすい。 1度作られたクラスタは次にクラスタになりにくい性質、 (=あちこちでバランスよくクラスタが作られていって最後にそれぞれがまとまる性質) を空間拡散性というらしい。ほぅ。下の図は空間拡張性が無いことを表す。 クラスタ数を多くしていったとき、空間拡張性がないと\"でかいクラスタ\"と\"小さいクラスタ\"が共存する アンバランスな構造になりそう。 距離の単調性 以下は重心法を使った場合。 重心法というのは、クラスタとクラスタの距離として各クラスタの重心間の距離を使う方法。 まぁ妥当な距離な感じがするが..。 本来は、同時多発的にクラスタが出来上がり、より大きくなるにつれて、 より遠いクラスタと併合するのが\"あるべき姿\"なのだけれども、 1度クラスタがくっつくと、他のクラスタとの距離が以前よりも小さくなってしまう状態が発生する。 距離の単調性がない、というらしい..。むむ. dendrogramの縦方向はクラスタ間距離なので、 距離の単調性があるのであれば、左右の部分木は両方とも下方向に伸びるはず。 無いのであれば、左右のいずれかが上方向に伸びる。 ward法を使った場合 以下はWard法を使った場合。詳細は以下。無茶苦茶面倒臭い。 [clink url=\"https://ikuty.com/2019/07/09/hierarchical_clustering/\"] 空間拡散性、距離の単調性があって(バランス木という言葉は全然違うが..) バランス良く木ができている。 データ数が多すぎて全然見えないけど...
6個のデータポイント近隣に発生させたデータ達を6-meansでクラスタ分割できるか
multivariate_normalを使って6個のデータポイント近隣にデータ達を発生させる。 薄くクラスタを見つけられそうだけれど境界は曖昧で大分被っているという状況。 そんなデータ達に6-meansをかけてみたとき、どうクラスタが出来るのかという実験。 被っている部分がどう別のクラスタに入るのか確認するため。 import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt import seaborn as sns mu = [[0,0], [20,20], [50,50], [40,30], [40,10], [20,40]] sigma = [ [[30,20],[20,50]], [[20,30],[10,20]], [[60,40],[20,20]], [[60,20],[20,60]] ,[[30,10],[10,30]],[[50,20],[20,50]] ] points = 100 clusteres = [] for index in range(len(mu)): cluster = np.random.multivariate_normal(mu[index], sigma[index], points) dig = np.full((points,1),index+1, dtype=int) cluster = np.hstack((cluster,dig)) clusteres = np.r_[clusteres,cluster] if len(clusteres) > 0 else cluster plt.scatter(x=clusteres[:,0], y=clusteres[:,1],c=clusteres[:,2]) おもむろにsklearnのKMeansを使ってみる。 n_clustersは6、max_iterを10に設定してみた。 クラスタ中心がわかるように重ねてみた。 from sklearn.cluster import KMeans kmeans_model = KMeans(n_clusters=6, init=\'random\',max_iter=10).fit(clusteres[:,:2]) labels = kmeans_model.labels_ centers = kmeans_model.cluster_centers_ centers fig = plt.figure() ax1 = fig.add_subplot(1,1,1) ax1.scatter(x=clusteres[:,0], y=clusteres[:,1],c=labels) ax2 = fig.add_subplot(1,1,1) ax2.scatter(x=centers[:,0], y=centers[:,1], alpha=0.5,s=600,c=\"pink\",linewidth=2,edgecolors=\"red\") 当然のごとく、微妙に被っていた部分は異なるクラスタに分類された。 今回は当たり前なことを確認して終了。 2次元データじゃつまらない...。
自力で生成したデータポイントに対して自力でクラスタ分割してみる
クラスタリングについて凄まじくわかりやすい説明を聞いて感動しました。 k-meansを自力で書くことで理解が深まりそうなので、参考にしながらアプトプットしてみます。 前回のエントリで、多次元正規分布に従う標本を作れるようになったので、 もともと存在する中心から適当に散らばるように作ったデータポイントに対して、 どの程度クラスタ分割できるのか確認する例です。 見てわからないと仕方がないので2次元とします。 早速、2つの中心から適当に散らばるようなデータポイントを作ってみます。 cluster1 = np.random.multivariate_normal([-10,-10], [[20,10],[30,20]], 100) cluster2 = np.random.multivariate_normal([10,10], [[50,5],[5,50]], 100) X = np.r_[cluster1, cluster2] plt.scatter(X[:,0], X[:,1]) 合計200個の点に、確率0.5でラベル1を振って(=確率0.5でラベル0)、 それぞれ色を付けて表示してみます。これを初期クラスタとします。 0クラスタ、1クラスタそれぞれ混じっていて、このままでは適切なクラスタ分割ではありません。 y = np.random.binomial(n = 1, p = 0.5, size = 200) plt.scatter(X[:,0], X[:,1],c=y) ラベル0のデータをX1、ラベル1のデータをX2という風に名前を付けて、 pandasデータフレーム化します。 さらに振ったラベル列を付けます。列追加は.assign()で出来るみたい。 import pandas as pd center = pd.DataFrame(X, columns = [\"X1\", \"X2\"]) center.shape # (200, 2) center = center.assign(y=y) center.shape # (200, 3) 0クラスタと1クラスタでまとめます。SQLで言うところのGroupBy句。 メソッド名もまんまgroupbyなのでわかりやすい。 GroupByした後、平均を計算する。0クラスタ、1クラスタ毎のX1,X2の平均が出ているっぽい。 center = center.groupby(y).mean() # X1 X2 y # 0 -1.701594 -1.186065 0 # 1 1.278607 0.954203 1 いよいよ、各データポイントのクラスタを更新して、適切なクラスタに振っていきます。 pandasデータフレームからNumPyのArrayを取るのは結構面倒くさい。 locにより行を取得できる。その際pandasの列名を指定できる。 SQLでSELECT書いているのに近い。 クラスタ0、クラスタ1それぞれのデータポイントについて、 各クラスタにおけるクラスタ中心と距離を求めます。距離は2乗和。 center_cluster_0 = center.loc[0, [\"X1\", \"X2\"]].values center_cluster_1 = center.loc[1, [\"X1\", \"X2\"]].values center0 = center.loc[0,[\"X1\",\"X2\"]].values center1 = center.loc[0,[\"X1\",\"X2\"]].values dist0 = (X[:,0].reshape(200) - center0[0])**2 + (X[:,1].reshape(200) - center0[1])**2 dist1 = (X[:,0].reshape(200) - center1[0])**2 + (X[:,1].reshape(200) - center1[1])**2 クラスタ0のクラスタ中心との距離よりも、クラスタ1のクラスタ中心との距離の方が大きいということは クラスタ0に属するべきです。論理式の結果がTrueかFalseかのいずれかになることを使って 2つのクラスタに分けます。かなり無理やりな気がします。 真偽の扱いですが、Pythonの言語仕様上、0か0に類する値はFalse、それ以外はTrueです。 new_cluster_id = dist0 < dist1 元Webプログラマが普通にforを使って書いてみると以下の通りとなります。 new_cluster_id2 = [] for index in range(len(dist0)): new_cluster_id2.append( 0 if (dist0[index] < dist1[index]) else 1) np.reshape(new_cluster_id2,200) 生成した入力値に新しいクラスタIDを振って色分け表示してみます。 new_cluster_id = dist0 < dist1 plt.scatter(X[:,0], X[:,1], c = new_cluster_id) 綺麗にわかれた気がしますが、大元のクラスタが交差する部分において、 別のクラスタに分類されたデータがあるようです。